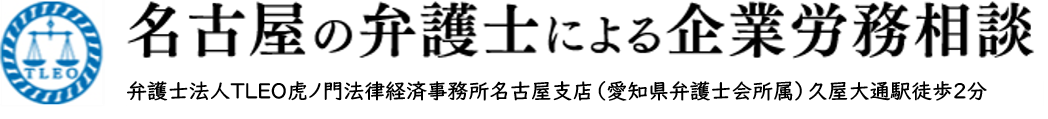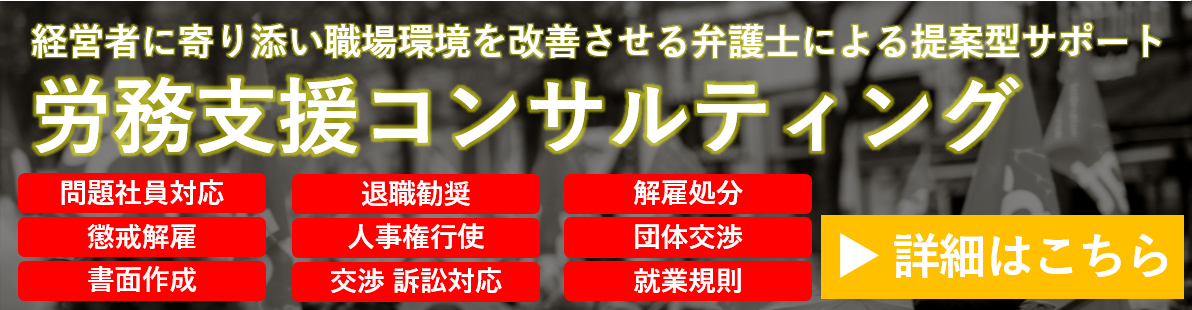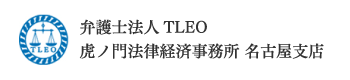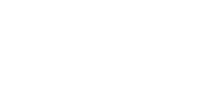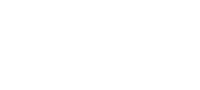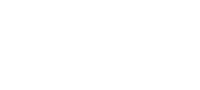メンタルヘルス不調社員の復職可否が問題となった事例

| 相談企業のエリア | 愛知県東部 |
| 相談企業の業種 | 製造業 |
| 相談企業の従業員規模 | 50名程度 |
| 相談のジャンル | メンタルヘルス |
| 争点 | 復職の可否 |
相談前の状況
A社の従業員Bは、勤務中にパニック障害の症状が生じ、欠勤を経て休職することとなりました。従業員Bは、早期の復職を希望していましたが、A社の工場では大型の機械を使用するなど身体への危険が伴うため、再びパニック障害の症状等が出た場合には労務災害が起きることなどが心配されました。このため、A社は従業員Bを直ちに復職させることは望ましくないとして、しばらく休職をするよう伝えました。
そうしたところ、従業員Bは弁護士を代理人に立てて、従業員Bがパニック障害を発症したのは過重労働と上司による不適切な指導が原因であるなどとして慰謝料等の請求をするとともに、速やかな復職を要求してきました。こうして、A社は当事務所に従業員Bへの対応を相談されました。
相談後の提案内容・解決方法
勤務状況等を把握したところ、従業員Bの労働時間は一般的に精神障害を発症させるほど多くなく、6か月単位で見てもパニック障害との関連性は否定されるものと判断し、慰謝料請求等には応じられない旨回答しました。
また、直ちに復職させた場合には、かえって使用者としての安全配慮義務違反等を問われかねないため、従業員Bの症状や発症原因、復職に当たって注意すべき点等について主治医への聞取りをさせてほしい旨要請を出しました。
このように、復職に向けた慎重なプロセスを提示し、対応をすることで、休職期間の延長を繰り返しながら、従業員Bは最終的に退職するに至りました。
担当弁護士からの所感
休職事由が精神的な疾患にある場合、その回復までには相当程度の時間を要することが多いと思います。労働者の側としては、じっくりと長期間休職したいと希望する者もいれば、逆に早期の復職を希望する者もいます。こうした場合、使用者である企業としては、単純に労働者の希望だけで休職もしくは復職を判断することは、安全配慮義務の問題や企業秩序の観点からも適切ではありません。
復職を巡っては、休職の理由となっている傷病が「治癒」すれば復職となりますが、どの程度まで回復すれば「治癒」したといえるのか、復職後は軽減業務に就かせるべきなのか、ということがしばしば問題となります。復職の可否を判断するに当たっては、主治医の診断書を無視することはできませんが、主治医が正確に労働環境を理解しているとも限りません。このため、企業側としては、主治医との面談の機会を作るよう申し入れることが望ましいケースが多いと考えます。
本件では、こうした点を踏まえて復職に向けたプロセスを提示するなどして対応し、休職期間を延長しながら労働者と企業双方にとって穏当かつ適当な解決を図ることができました。
関連のある当事務所のサービスについてはこちらから
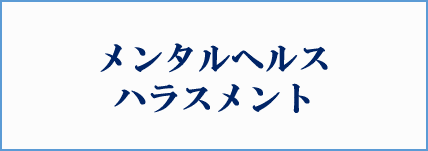 |
 |
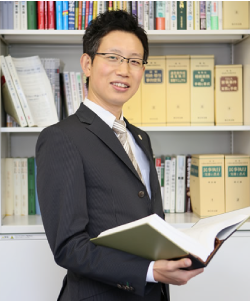
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。