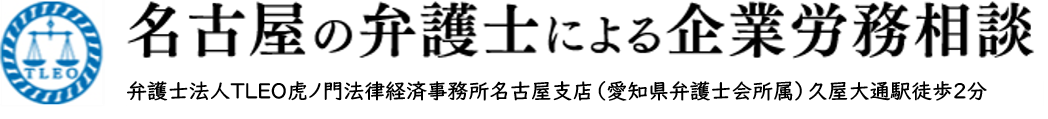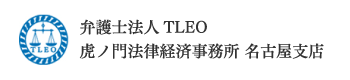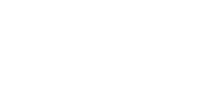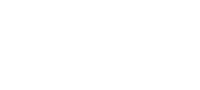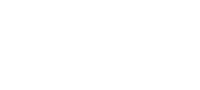就業規則がなければできないこと
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、法的な視点から就業規則の作成・変更・届け出に関するご提案をするとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことも可能です。就業規則の作成・変更でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
就業規則は会社が定めるルール

就業規則は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、その作成と行政官庁への届出が義務付けられています(労基法89条)。「労働者」には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員など雇用形態の如何を問わず当該事業場で働く者が含まれますので、たとえ正社員の人数が少なかったとしても、ある職場で働く総数が10人以上となる場合には就業規則の作成義務が課されます。もっとも、労働者の数が必ずしも10人以上でなくとも、従業員を一人でも雇っているのであれば、すべての企業において就業規則を作成すべきでしょう。
なぜなら、使用者と労働者は対等な関係にあり、「なんでも会社の自由にできる」わけではいからです。使用者が労働者に守ってもらいたいこと、あるいは権限を行使したいことがあるのであれば、そうしたルールを作らないといけません。そして就業規則こそが、企業側から労働者側に、働くにあたって守るべき規律を一方的に示すことができるルールブックなのです。会社が、こういうことはしてはいけない、こういうことをしたらこんな処罰を受ける、働く時間はこうだなどと、会社が好きなように定めたルールを明文化したものが就業規則です。好きなように定め、そしてそのとおりに従業員を規律できるのですから、こんな良いものを定めない理由はありません。
もちろん、「好きなように」定めることができるとはいっても、労働基準法をはじめとした法律に違反してはいけないことは当然です。また、就業規則のとおりに従業員を規律するためには、労働法規を理解したうえでそれを適切に運用することも必要となります。こうした押さえるべきところを押さえて使いこなすことができれば、就業規則は会社自身が定めるルールブックとして、会社に大きな便益をもたらしてくれることになるでしょう。
労働者の意見聴取義務
就業規則の作成・変更にあたっては、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の意見を聴かなければならないとされています(労基法90条1項)。
これは文字どおり「意見」を聴くことが必要なだけであり、労働者側の「同意」を得る必要はなく、また就業規則の内容について「協議」をする必要もありません。したがって、結局、使用者には就業規則の一方的な制定権があるということになります。
就業規則がなければできないこと
就業規則がない場合に、使用者が権限(命令)によって行うことができないことの代表例を以下に挙げますが、これらに限らず、就業規則の定めがあってはじめてできることは他にも数多くあります。なお、就業規則そのものがない場合であっても、雇用契約書にその定めが置かれている場合にはそれらを行うことも可能になりますが、就業規則を作成していないような場合、詳細な規定を持った雇用契約書を作成しているということはまれなように思います。
1.懲戒処分
懲戒処分は、懲戒の事由と手段を就業規則に定めることによってはじめて行うことができるようになります。したがって、どのような場合にどのような懲戒手段をとることができるかを明記しておかなければ、いざという時に身動きができなくなってしまいます。また、「使いやすさ」が大事ですので、定める場合はあまり入り組んだ複雑な規定としないように気を付けたいところです。
2.人事異動
人事異動には、①転勤、②配置転換、③出向、④転籍の4つの形態があります。たとえば、もともと名古屋だけで事業を行っていた会社が新しく東京にも支社を出す場合に、ある従業員に東京に行ってもらおうとすれば、これを命令によって行うためには就業規則の根拠規定が必要となります。打診したところ、「はい、喜んで」と従業員からの同意がある場合には有効に転勤をさせることができますが、職務命令として行う場合には就業規則の定めが必要です。
3.時間外労働・休日労働
いわゆる「残業」と呼ばれる時間外労働・休日労働を行わせるためには、36協定の締結と労基署への届出が必要となりますが(労基法36条)、これは1日8時間・1週40時間、あるいは週休制の原則(労基法32条、35条)を超える労働をさせるためのいわば許可を得るものに過ぎません。残業を業務命令によって行わせるためには、36協定とは別に、就業規則において業務上の必要があるときは時間外労働・休日労働を命じ得る旨が定められていることが必要です。
4.振替休日・代替休日
休日と定められていた特定の日に働かせる代わりにその前後の労働日である特定の日を休日に変更する休日振替を行う場合にも、それを命令として行う場合には就業規則による根拠が必要となります。
なお、休日と労働日を事前に変更する「休日振替」と異なり、休日労働をさせた後に代休日を付与する場合には、休日労働に対する割増賃金(労基法37条)の支払が必要となりますので注意が必要です。
5.休業手当の6割支給
使用者側の都合によって労働者を休業させる場合、使用者は休業期間中の賃金を100%支払わなければならないのが原則です(民法536条2項)。この民法の原則は任意規定と呼ばれるもので、これと異なる内容の取り決めをすれば、民法の規定に従う必要はなくなります。他方で、労働基準法は、使用者都合による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払いを使用者に義務付けています(労基法26条)。これは休業の場合における労働者の最低生活の保障を図る趣旨で定められたものですので、強行規定として使用者は必ず従わなければなりません。
このようなことから、就業規則において民法の適用排除を定めることによってはじめて、使用者は休業手当6割の支給による会社都合の休業を行うことができるようになるのです。
6.賃金からの控除
賃金支払いの5原則と呼ばれるものの一つに、「全額払いの原則」があります(労基法24条)。賃金はその全額を支払わなければならない、という原則で、使用者は賃金から勝手に色々な名目のものを控除することはできません。
もっとも、たとえば会社が金銭を従業員に貸付けた場合、その返済を賃金からの控除によって行いたいと考える場合もあります。これを適法に行うためには、賃金控除の労使協定を労働者代表との間で締結するとともに、就業規則にその旨(労使協定による控除の根拠規定)を定めておくことが必要となります。
労務管理には専門家の支援を
ここでは就業規則があることによってはじめて使用者による権限行使が可能な事項等について説明をさせていただきました。就業規則に関しては、こうした理解を踏まえて、就業規則の各条項の定め方などについても法的事項を踏まえて検討を行い、使用者が予期しない不利益を被らないように適切に作成・変更・運用をする必要があります。
労働規制は複雑なうえに、その理解と運用を誤れば経営を揺るがしかねない大きなリスクを企業にもたらします。労務管理については、労働問題に強い弁護士などの労務の専門家の支援を受けながら、制度設計と運用をされることを強くお勧めいたします。真面目に経営をされている経営者の皆様が、法を「知らなかった」、あるいは「軽んじていた」がために、苦しい思いをされることが少しでもなくなるようにと願っています。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】

岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは
労働コラムの最新記事
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは