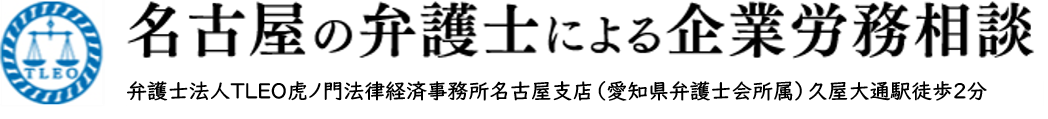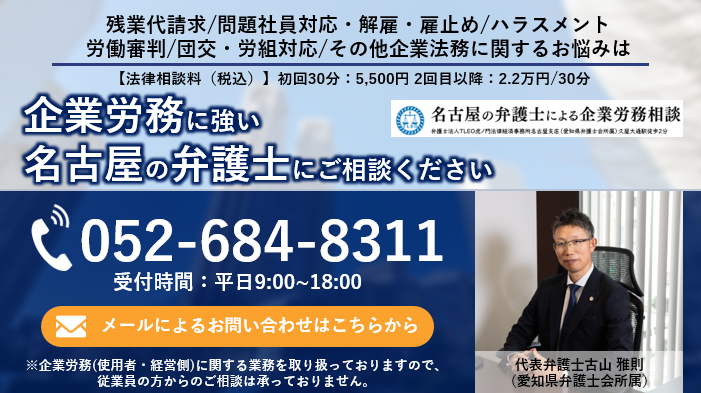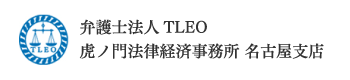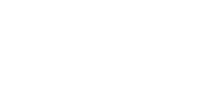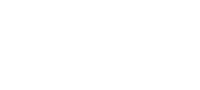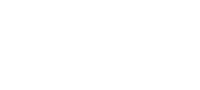行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
虎ノ門法律経済事務所名古屋支店では、労働組合との交渉を有利に進めるための方法をご提案するとともに、解雇や未払残業代問題、休職問題など各テーマ別ノウハウに基づいたご支援をさせていただくことが可能です。合同労組やユニオンなどの労働組合との交渉でお困りの会社様は、是非一度当事務所にご相談ください。
本記事で書かれている内容
団体交渉の行き詰まり
 使用者には、団体交渉において誠実に交渉に応じる義務が課せられています(労働組合法7条参照)。ユニオン、合同労組などの労働組合は、この誠実交渉義務を背景にして、団体交渉が進展しないことや、あるいは交渉を打ち切ろうとする使用者の態度を捉えて、「不誠実で不当労働行為にあたる」などと使用者を責め、交渉を有利に運ぼうと強硬な態度で臨んでくることが往々にしてあります。しかしながら、使用者は誠実に交渉に応じる義務はありますが、要求事項に対して譲歩する義務はありません。誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索したものの、結果として意見の一致をみないまま交渉が破談となることは、誠実交渉義務違反とはなりません。そのため、十分な交渉を重ねたものの、労働組合・使用者いずれかの譲歩によって交渉が進展する見込みがなく、団体交渉を継続する余地がない状況となったのであれば、使用者は団体交渉を打ち切ることが可能です。
使用者には、団体交渉において誠実に交渉に応じる義務が課せられています(労働組合法7条参照)。ユニオン、合同労組などの労働組合は、この誠実交渉義務を背景にして、団体交渉が進展しないことや、あるいは交渉を打ち切ろうとする使用者の態度を捉えて、「不誠実で不当労働行為にあたる」などと使用者を責め、交渉を有利に運ぼうと強硬な態度で臨んでくることが往々にしてあります。しかしながら、使用者は誠実に交渉に応じる義務はありますが、要求事項に対して譲歩する義務はありません。誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索したものの、結果として意見の一致をみないまま交渉が破談となることは、誠実交渉義務違反とはなりません。そのため、十分な交渉を重ねたものの、労働組合・使用者いずれかの譲歩によって交渉が進展する見込みがなく、団体交渉を継続する余地がない状況となったのであれば、使用者は団体交渉を打ち切ることが可能です。
もっとも、こうした行き詰まり状態となった団体交渉の打ち切りが簡単ではないのも事実です。「誠実」か「不誠実」かは一つの評価であり、労働組合は使用者側の態度が不誠実であると強硬に主張してくるでしょう。このような場合にいきなり団体交渉を打ち切るのは、不当労働行為の救済申立てがなされるリスクがあるうえ、ビラ配りや街宣活動等の団体行動を招くリスクを高めることにもなるため、なかなか交渉打切りに踏み切れないのが現実です。そこで、行き詰まり状態となった団体交渉を打破するため、「労働委員会のあっせん」を活用することが考えられます。
使用者によるあっせん申立ての活用
労働委員会のあっせん
「あっせん」とは、あっせん員が関係当事者間をとりもって、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決するように努める手続です。労働委員会は、労働関係調整法に基づき、労働者・労働組合と企業との間に入って労働争議を調整します。なお、労働委員会のあっせんの対象となる労働紛争には、個別的労働関係に関するものと団体的労使関係に関するものの両方が含まれます。もっとも、団体的労働紛争(集団的労働紛争)であっても、従業員が合同労組、ユニオンに駆け込み、その労働組合との間であっせんが行われることが多いため、実態としては個別労働紛争をめぐる問題で大部分が占められているといっても良いかもしれません。
企業によるあっせんの利用
このあっせん手続は、これまでそのほとんどが労働者あるいは労働組合側により利用されていました。裁判や労働審判等の司法手段に比べて手続きが簡易で使い勝手が良いため、労働紛争の解決手段の一つとして利用されています。
企業側から労働紛争に関して労働者を積極的に訴えることが少ないのと同じように、企業はこのあっせん手続をあまり利用してきませんでしたが、実は企業にとっても労働組合との団体交渉上の問題を解決するうえで有力な手段となり得ます。
日本経済新聞の2019年7月29日朝刊でも、企業があっせんを利用して紛争を解決する様子が紹介されており、その利用法が注目されています。
同記事では、団体交渉を担当していた社員が不慣れな団体交渉によって言動や判断が乱れるなど精神的に不調になったことを背景として、企業が労働委員会に駆け込み、あっせんを通して団体交渉の仕切り直しを行った事例が紹介されています。また、ユニオンへの対応に失敗し、会社や取引先の本社前などで団体行動権の行使として宣伝活動をされ、慌ててあっせんを求める企業が目立つとの話も聞かれます。
2017年度のあっせん開催数は全国で278件と5年前から4割減少していますが、使用者側からの申立の割合はそのうち10.6%と5年前より3ポイント近く上昇しています(同記事)。
労働委員会のあっせん手続の概要
手続の流れ
1 あっせんの申立て
労働者、労働組合又は使用者が申請書を労働委員会に提出します。
労働争議が一の都道府県の区域内のみに係るときはその都道府県の労働委員会の管轄となり、複数の都道府県にわたるときは中央労働委員会の管轄となります。
2 あっせん員の指名
労働委員会の会長は、あっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。あっせん員は、公益、使用者、労働者側のそれぞれを代表する公労使の三者構成となるのが基本ですが、都道府県によっては事務局職員が指名されることも多く行われているようです。
3 相手方への確認・調査
労働委員会の事務局が、申立てを受けた相手方に対して、あっせんを受けるか否か、申立内容に関する意見や考え方等を確認・調査します。
相手方はあっせんに応じる義務はないため、相手方があっせんに応じない場合、あっせんは開催されることなく打ち切られることになります。
4 あっせんの開催
当事者は、あっせんの期日に出席しなければなりません。あっせん員は、当事者それぞれから事情を聴取し、紛争の争点を整理します。
5 あっせん員による調整
聴取した事実関係を踏まえて、あっせん員は労働紛争の調整を試みます。互いの本音や妥協点を探りながら、解決に向けた働きかけが行われます。
6 あっせん案の提示
当事者双方の折り合いがつく可能性が見えてきた場合には、あっせん員からあっせん案が出されます。対立が激しく解決の見込みがないと判断される場合は、あっせん案が出されないままあっせん打ち切りとなることもあります。
7 合意又は打ち切り
当事者双方があっせん案を受け入れる場合は、あっせん案に合意して紛争が解決されます。当事者どちらか一方でもあっせん案を拒否する場合は、あっせんは打ち切りにより終了します。
愛知県における利用状況
愛知県労働委員会におけるあっせん手続の利用状況は次のとおりとなっています(2019年6月30日時点、労働委員会事務局HPより)。
団体的労使紛争
・平成26年度 17件(内解決5件)
・平成27年度 18件(内解決6件)
・平成28年度 18件(内解決5件)
・平成29年度 14件(内解決7件)
・平成30年度 8件(内解決4件)
・平成31年度(4~6月期) 4件(内解決2件)
個別労働関係紛争
・平成31年度(4~6月期) 4件(内解決0件)
使用者によるあっせん利用-まとめ
現時点では使用者側の申立によるあっせんの件数自体は少ないですが、新聞でも取り上げられているように、活用次第では、労使紛争を解決する有効な手段となるのが労働委員会のあっせん手続です。団体交渉がこう着状態となり事態を打開する場合や、交渉打ち切りによる不当労働行為性を排除するためにも、あっせんの利用は有力な選択肢となり得ます。企業は是非、労働組合との難しい団体交渉を突破する一つの手段として、労働委員会のあっせん手続を活用いただければと思います。
▼弁護士による対応の詳細はこちらから▼
弁護士による団体交渉、労働組合対応とは?対応の流れについて解説!
団体交渉には専門家の支援を
合同労組、ユニオンなどの労働組合は、労働問題についてある種のプロフェッショナルであり、豊富な団体交渉の経験を有しています。企業がこうした労働組合と対峙するにあたり、十分な対抗策を用意しないまま交渉に臨めば、意図しない不利益な結果を甘受しなければならなくなる危険があります。企業防衛のためには、労働問題に強い弁護士などの支援を受けながら団体交渉に臨まれることを強くお勧めいたします。専門家の支援を受けることで、企業は過酷な交渉の負担から解放され、適切な方針のもと最良の解決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。
当事務所では、予防法務の視点から、企業様に顧問弁護士契約を推奨しております。顧問弁護士には、法務コストを軽減し、経営に専念できる環境を整えるなど、様々なメリットがあります。 詳しくは、【顧問弁護士のメリット】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
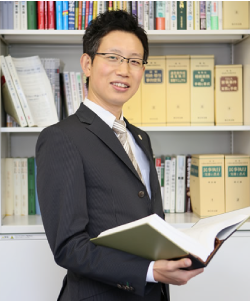
岐阜県出身。中央大学法科大学院卒業。経営者側に立った経営労務に特化し、現在扱う業務のほとんどが労働法分野を中心とした企業に対する法律顧問業務で占められている。分野を経営労務と中小企業法務に絞り、業務を集中特化することで培われたノウハウ・経験知に基づく法務の力で多くの企業の皆様の成長・発展に寄与する。
関連記事はこちら
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 行き詰った団体交渉を打破する‐あっせん手続の活用
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
労働コラムの最新記事
- 問題社員対応を見据えた就業規則の作り方とは?弁護士がポイントを解説!
- 社用車の自損事故での自己負担の割合とは?従業員に弁償させたい場合の流れについて弁護士が解説!
- 競業避止義務を定めた誓約書提出の強制・義務付けの可否~違反した場合・誓約書の効力について~
- 【コラム】退職後の競業避止義務違反を防ぐ! -競業避止契約と違約金の定め-
- 【コラム】競業避止義務に違反した退職社員に対して退職金の返還請求をする!
- 【コラム】年功序列型賃金の限界と人事制度改革
- 【コラム】同業他社への転職を防ぐ誓約書作成の勘所 - 抑止力ある競業避止義務を課すために
- 【コラム】年休取得時に支払う賃金-各種手当は「通常の賃金」に含まれるか
- 【コラム】業務上の負傷・疾病で療養・休業を続ける従業員を解雇できるか?
- 【コラム】運送業者必!歩合給の制度設計と賃金制度変更の手引き
- 【コラム】運送業者必見!残業代リスクを大幅に軽減する賃金制度設計
- 【コラム】運送業者必見!高額化する残業代請求リスクに備えあれ
- 内部調査等に従事する者の守秘義務とは?-改正公益通報者保護法
- 実労働時間がタイムカードの打刻時間どおりでない場合
- 退職した従業員から損害賠償請求をされた際の会社側の対応方法とは?事例を基に弁護士が解説!
- 雇い入れ時の健康診断は省略可能か?-定期健康診断での代用・入社後/退職予定者への対応策について!-
- 36協定の締結を労働組合に拒否された!-残業・時間外労働・結びたくないと言われた会社にとってのデメリットとは?弁護士が解説!
- 70歳までの継続雇用-改正高年齢者雇用安定法に対する企業の向き合い方
- 経歴詐称の社員を解雇したい!
- 社員が始末書を提出しない!
- 懲戒処分の社内公表はどこまで可能?社内通知に注意点・判断基準について弁護士が解説!
- 企業の採用の自由と調査の自由
- 定年後再雇用を辞めさせる方法はありますか?-継続雇用制度と嘱託社員の雇止め・再雇用者の契約終了(契約打ち切り)について弁護士が解説!
- コロナ禍における労務対応‐在宅勤務とフレックスタイム制
- 懲戒処分には弁明の機会の付与が必要?-懲戒解雇の進め方や団体交渉への弁護士の同席について解説!
- 傭車運転手からの団体交渉‐業務請負者と労組法上の「労働者」
- 移動時間と労働時間について-出張での移動時間や勤務時間について弁護士が解説!-
- 退職勧奨はどこまでできる?-「辞めるつもりはない」とはっきり言われたら
- 有期契約社員の雇止め-契約社員から雇止めが不当だと主張されないために
- 濫用的年休申請への対処法
- 余剰人員の削減!でも中小企業が整理解雇を行う前にやるべきこと
- タイムカードでの残業代・残業申請について弁護士が解説!打刻での時間外労働の計算方法について
- 在宅勤務のための費用は会社が負担すべきか?-テレワークにおける費用負担
- 企業の街宣活動への対応方法とは?-違法となる場合・街宣車がうるさい場合は通報できる?-
- 身元保証契約には極度額の定めが必須!-民法改正への対応
- 不況時の人員削減‐中小企業のための整理解雇実行の手引き
- 派遣事業の適法性リーガルチェック‐派遣業と請負業
- 派遣先から減産による休業措置がとられたら‐休業時に派遣会社がとるべき対応
- 団体交渉で休業補償100%を求められたら‐休業と休業手当
- テレワーク導入の手引き‐弁護士がすすめるテレワーク規定の要点と成果を上げるための4つの視点
- 経営上の理由により従業員を休ませる場合の対応‐休業補償と政府による休業支援策
- 労働者派遣契約-契約事項と情報提供義務
- 労働者派遣事業の許可‐派遣事業を始める方へ
- 派遣労働者の同一労働同一賃金
- パワハラ対策が義務化!-パワハラ防止法
- 労働者の健康管理-医師による面接指導義務
- 社内に労働組合ができたらどう対応するか‐労働組合の要件
- 労基法改正-新たな残業規制
- 年5日の年次有給休暇の取得が義務化
- 経営者必見!定額残業代制に関する重要判決と時代の変化への対応
- 経営者必見!定額残業代制が否定された場合の三重苦
- 労災事案の賠償請求に対する使用者側対応と労災保険
- 外国人労働者への労働関係法令の適用と社会保険
- 不法就労の防止と対応
- 外国人技能実習生の受入手続
- 派遣労働者への労働条件の通知と就業条件の明示
- 労働者派遣期間の制限と適正な運用
- 相次ぐ技能実習認定の取消し‐外国人材受入れ企業はより一層のコンプライアンスを
- 派遣契約の終了と派遣労働者の処遇
- 「残業代込みの給料」-定額残業代制の留意点
- 季節により繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制で時短を
- 予期しない残業代請求を受けないための就業規則の規定と運用
- 間違えると取り返しがつかない!-就業規則「賞与(ボーナス)」の定め方
- 就業規則における懲戒の定め方について解説!~出勤停止の期間について~
- 残業代に含まれる手当とは?計算方法について弁護士が解説-基礎賃金に含まれる手当とは?家族手当は含まれる?残業手当・固定残業代について弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例③(従業員に損害賠償を請求したい!)~モンスター社員対応~
- 変形労働時間制は運用が鍵!
- 残業代請求を和解で解決する場合の注意点-和解と賃金債権放棄
- 労働委員会への救済申立てに対する対応
- 降格処分はこう使う!
- 無期転換ルールへの対応-有期契約社員の更新、雇止めと就業規則の改定
- 日常業務に関する事項と団体交渉
- 労働条件の不利益変更-就業規則の修正・変更は自由にできるか?
- 就業規則がなければできないこと
- 従業員への貸付金の返済金を賃金から適法に控除する方法
- 残業許可制でダラダラ残業を防ぐ!
- それって労働時間にあたるの?-手待ち時間の労働時間該当性
- 就業規則に潜む危険-雛形をそのまま使っていませんか?
- メンタルヘルス問題と使用者の損害賠償責任
- 円満に内定取消を行う方法
- 求人票記載の給与額と契約上の給与額
- 経営事項と団体交渉
- 賞与(ボーナス)を巡る問題と団体交渉
- 会社を守る36協定の締結方法
- 残業単価の計算方法とは?-時間単価・労働時間について弁護士が解説!-
- メンタルヘルス不調社員対応のポイント
- 使用者のためのマタハラ、育児・介護ハラスメント対応の手引き
- 「残業代」とは何か?- 割増賃金が発生する3つの「労働」
- 残業時間の立証-使用者による労働時間の適正把握義務
- 管理職と残業代請求-管理監督者とは
- 恐ろしい残業代未払いに対するペナルティとは?残業代請求は拒否できる?-遅延損害金についても弁護士が解説!-
- 問題社員対応事例②(従業員が会社のお金を横領した!)~モンスター社員対応~
- 問題社員対応事例①(ローパフォーマー社員を辞めさせたい!)~モンスター社員対応~
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き③(パワハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き②(セクハラ編)
- 使用者のためのセクハラ・パワハラ問題対応の手引き①(基礎知識編)
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part3
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part2
- 使用者側・労働審判を有利に導く10のコツ Part1
- 懲戒処分を行う場合の留意点
- 退職金の減額・没収・不支給
- 能力・適格性が欠如する問題社員対応のポイント
- 雇止めと団体交渉
- 解雇無効についての団体交渉
- 未払い残業代請求についての団体交渉
- 団体交渉を有利に進める方法
- 元従業員との団体交渉
- 団体交渉に弁護士を入れることのメリット
- 団体交渉申入書が届いたら
- フレックスタイム制の活用法
- 働き方改革③-高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)とは
- 働き方改革②-同一労働同一賃金とは
- 働き方改革①-新しい残業規制とは